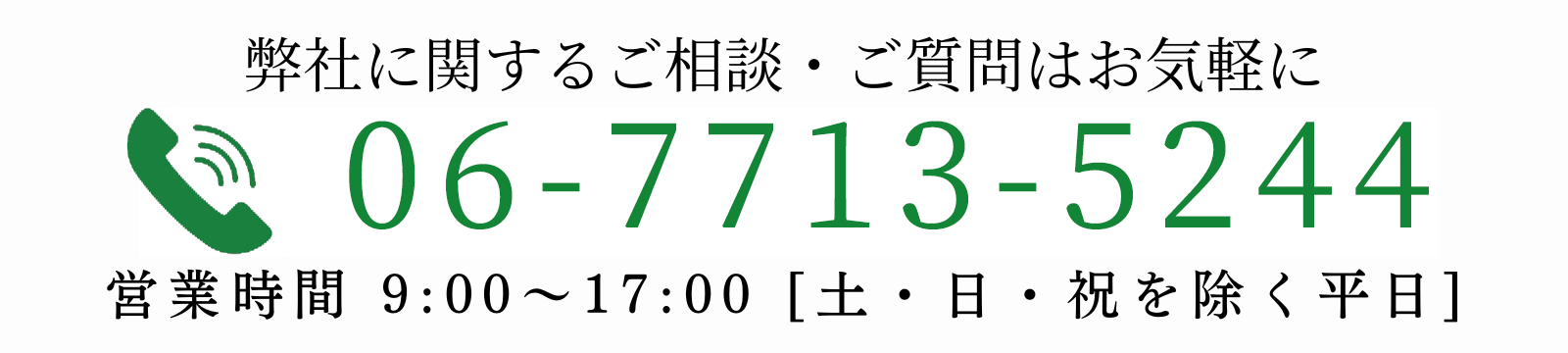
帰化申請サポート
日本に長く住み、生活基盤を築いた外国人の方が日本国籍を取得するためには「帰化申請」が必要です。帰化申請には厳格な審査があり、法務大臣の許可を得なければなりません。
当事務所では、多くの帰化申請をサポートしてきた実績がございます。
ここでは、帰化申請の主な要件と、実際に取り扱った事例の一部をご紹介します。
帰化許可の主な要件
帰化申請には、以下のような要件を満たす必要があります。
1. 住所要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。留学生の場合は留学期間が半分とみなされます。
【事例】
- 留学4年+就労3年で合計5年とみなされ、申請可能となったケース
- 年間100日以上の帰国がある場合はリセットとなり、帰国後改めて5年の住所要件が必要となります。仕事の都合など特別な理由がある場合は、理由書の提出が必要です。
- 研究のため200日以上海外に滞在した方は、帰国後改めて5年の住所要件を満たす必要があります。
2. 年齢・行為能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
20歳以上で本国の法律に基づき行為能力を有していることが必要です。15歳未満の方は親権者が代理で申請でき、その際は親権者と一緒に撮影した写真の提出が求められます。
3. 素行善良要件(国籍法第5条第1項第3号)
過去の犯罪歴や交通違反歴などがないことが求められます。
【具体例】
- 不法就労助長罪や薬物取締法違反がある場合は許可が難しくなります。
- 交通事故違反や軽犯罪法違反などは、違反の内容や時期、反省の有無によって審査に影響します。
- 家族の犯罪歴も確認される場合があります。
4. 生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
申請者本人または生計を一にする配偶者等の安定した収入や資産によって生活が成り立っていることが必要です。
【事例】
- 自己破産経験があっても、理由や経過年数によっては許可される場合があります。
- 親族の資産に依存する場合は、別居して生計を別にする必要があります。
- 生活保護受給中の場合は許可が難しいケースが多いです。
5. 国籍喪失要件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化により現在の国籍を失うことができる必要があります。
【国別の手続き例】
- 韓国:帰化許可後に領事館で国籍抹消手続きを行います。
- 台湾:帰化許可の前に台湾の国籍喪失の手続きが必要です。
- 中国:国籍証明書が必要で、申請中の出国制限など注意が必要です。
その他の留意点
- 日本語能力は小学校低学年程度の読み書きが求められます。
- 本国の企業や団体に所属している場合は影響があります。
- 兵役義務の有無(韓国・台湾籍の男性など)により申請可否が異なります。
- 家族に帰化申請に反対する方がいる場合は、状況によって申請に影響することがあります。
- 特別永住者は一部の書類が免除される場合があります。
帰化申請の流れ
1. 法務局または地方法務局に相談する
まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。
2. 帰化申請に必要な書類を集める
法務局で確認した必要な書類を集めます。本国からの身分関係を証明する書類について、ご本人にお願いすることもあります。日本で取得できる書類は委任状に署名等いただき、当方で取得します。
3. 帰化申請書類の作成
申請書類の作成をし、詳細はご本人に確認します。提出する書類を齟齬がないように確認しながら進めます。
法務局に書類の点検に行きます。収集した書類と記載した申請書を法務局の担当者に確認してもらいます。ほぼ書類がそろった段階で、ご本人の法務局担当者との面談の予約をさせていただきます。
4. 法務局での面談
法務局担当者とご本人と行政書士が書類について確認した後、ご本人が宣誓します。
法務局での面接受理から2~3ヵ月経った頃に法務局からご本人に連絡がきて、提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。
5. 法務局の調査
近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査です。法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。実際に自宅等に訪問してくることもあります。訪問される場合は事前に日付を指定されます。
6. 法務省への書類送付
法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は法務局から東京の法務省に送付されます。法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。
7. 許可または不許可の決定
許可の場合→後日法務局の担当者からご本人に電話があります。官報に名前が掲載されます。
不許可の場合→不許可の通知が届きます。
※申請から結果が出るまで6カ月~1年以上かかることが想定されます。その間も交通事故違反など気を付けていただくことをアドバイスします。
8. 帰化届の提出
法務局から連絡があり、帰化届が渡されます。それを住居のある市町村役場に持参すると戸籍が編製されます。在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。
当事務所の帰化申請サポート
帰化申請は書類収集や作成だけでなく、状況に応じた的確なアドバイスが不可欠です。当事務所ではこれまでの豊富な経験をもとに、スムーズな申請手続きをしっかりサポートいたします。
帰化申請をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

